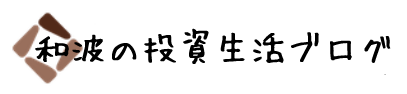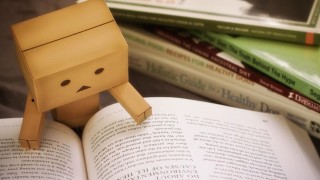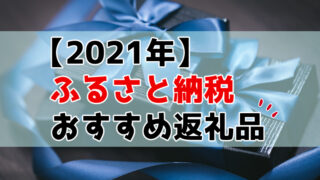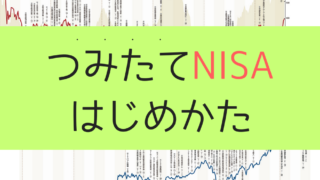今回はゼネラル・ミルズ(GIS)のファンダメンタル、チャート分析をやっていきたいと思います。
ハーゲンダッツの会社と聞いたらみなさん興味を持つのではないでしょうか。私はそうでしたw
一応、前に米国株の連続増配期待銘柄で取り上げています。13年連続増配なんですが、書き忘れたせいでこっちの記事にある^^;

ゼネラル・ミルズ(GIS)の事業内容
ビジネスを3Cで分解してみましょう。
事業内訳
ゼネラル・ミルズはハーゲンダッツ、とんがりコーンをはじめとした多数のブランドを展開する食品メーカーです。他にもシリアルはケロッグ(K)に次ぐ米国2位、ヨーグルトのヨープレイトが2位、冷凍ピザTotino’sが3位などなど、幅広い分野に横展開しています。
要するに「その業界の1位か2位を取る」という、GEみたいなリーダー戦略ですね。

(出典:ゼネラル・ミルズ)
食品業界というのは人口増&可処分所得増によって徐々に成長しますが、逆にいくら不景気だといっても人が生きるためには食べないわけにはいかないので、一定数の需要は継続する安定的な市場構成です。
また、一般的に食品生産する一次産業よりもゼネラル・ミルズのような加工産業のほうが付加価値がつけて差別化が出来るため、広告・マーケティングによって認知度を高めてブランド戦略を取ることが可能です。当然ブランド価値が高マージンを生みますし、そうしたブランドを複数有しているため、長期投資適格が高いのですね。
決算から
アニュアルレポートが非常に分かりやすくていいですね。イメージつきの目次があって、欲しい情報にワンクリックで飛ぶことが出来ます。

(出典:ゼネラル・ミルズ アニュアルレポート)

(出典:ゼネラル・ミルズ アニュアルレポート)
- US Retail(米国小売):全体の2/3を占めており、どちらかというと米国市場を主戦場としたグローカル企業ということが分かると思います(グローバルじゃないよ)。内訳はMeals(食べ物全般?)の24%に次いでシリアルが23%、スナックが21%です。
- International(海外売上):ヨーロッパが4割、アジアが2割です。直近の決算を見ると中国市場が+1%と成長しておらず、今一番小さなラテンアメリカは+12%と好調です。それにしても、利益率で見ると米国とそれ以外で倍以上の差がありますね。
- Convenience Stores and Foodservice(コンビニ):コンビニ的な小売もやってます。
最新決算も見ておきましょう。

(出典:ゼネラル・ミルズ)
実は7期連続の売上減少中となっており、上の決算でも前年と比較して各セグメントが落ちていることが分かります。米国小売の落ち幅が大きいですが、グリーンジャイアント等のブランド減損(その後売却)も響いており、M&Aでセグメント整理の最中です。
海外市場に目を向けると、落ち幅が小さいのはラテンアメリカ、逆に大きく落ちているのはヨーロッパや中国です。50%の国際ジョイントベンチャーの収益が倍増したとありますが、全体を見ると減っています。
理由を見ていると、主要ブランドの一つだったグリーンジャイアントの減損と、そのブランド売却、北米の野菜事業の不振、為替影響です。この減損処理が終わったことと、今後成長軸の有機食品にポートフォリオ整理が進んでいることから、どこかで反転するものと期待します。
※穀物、シリアル、スープ、ヨーグルトなどは市場シェア、利益率ともに良く、消費者の健康志向とマッチしているため、集中投資しようとしているようです(例えばチリオスをグルテンフリーに)。
競合
例えばシリアルではケロッグ(K)と、お菓子ではペプシコ(PEP)傘下のフリトレーや、米国最大のチョコレートメーカーのハーシー(HSY)と、なんか色々な食品ということでモンデリーズ・インターナショナル(MDLZ)あたりと競合していますが、結局製品ブランドごとに異なる競争相手がいるので、単純な比較は難しいです。

ただ、ゼネラル・ミルズはナンバーワンorナンバーツー戦略を取っていますので、競合は各市場1社か2社くらいです。
市場
米国市場中心で、かつ人口増が安定成長に寄与するということであれば、以下の記事で米国人口の増加について書いています。

とはいえこれだけだと味気ないので、加工食品市場をちょっと調べてみました。

(出典:みずほ銀行)
世界的には米国、中国をはじめとして安定的な成長を持続させる見込みです。個別に見ていくと、健康機能に注目した食品需要が特に拡大するようで、オーガニック、グルテンフリー、アレルゲンフリー、フリーフロム食品というったキーワードがポイントになります。

(出典:みずほ銀行)
ゼネラル・ミルズの場合、大きな中国市場の高成長の波に乗り切れていないのが心配です。M&Aでポートフォリオを拡充したとしても、結局は地道な広告宣伝によってブランドを浸透させていくしかなく、成果は時間と投資額に比例します。
と考えると、V字回復はもう少し先かもしれないですね。今が仕込み時なんでしょうか。
リスク要素
食中毒的なリスク(ゼネラル・ミルズには混入なし)
大腸菌観戦が騒がれたことで、万が一という可能性を考えてゼネラル・ミルズは4500トンの小麦粉を自主回収しました。
参考米ゼネラル・ミルズ:小麦粉4500トンを自主回収-大腸菌感染の懸念で
特に検出はしていない段階ですが、事前に手を打ったということで、私としてはゼネラル・ミルズの経営に好感を覚えました。
原発管理を怠った某企業の末路のように、目先の利益を渋るといずれ最悪な形で返ってくるもので、私達投資家も目先の利益より向こう何十年という期間で見て最適な投資判断をしたいものです。
減配転落した場合
下に書きますが、ゼネラル・ミルズの特徴は連続増配ではないものの上場以来一度も減配せず100年以上配当を出し続けてきたということ。
この株主還元の強い企業というコミットを達成するためには安定した主力ブランドの生むキャッシュでは足りず、資金のやり繰りで事業売却や短期借入の形跡がしばしば見受けられます。
逆に言えば、そこまでして維持している以上、もし減配のニュースが出たら逃げた方がいいということです。それだけ本業がヤバイということですからね。
ゼネラル・ミルズ(GIS)の財務分析
PL
安定した横ばいですね。ここ2年少し下がり気味なのは上で見た通り。

ROEが高く、営業利益率はそれなりです。

BS
自己資本比率は3割前後で推移しています。この数字自体は可もなく不可もなしですが、ブランドを多数持っているので、安全性に疑問はありません。


CF
こちらも安定した水準ですが、やや投資CFが年々伸びています。
この中ではM&Aでオーガニックフードの買収や、逆にグリーンジャイアントの売却などが発生していたりするのですが、FCFは高い状態を維持しているということですね。

株主還元指標
配当性向は50%程度ですが、自社株買いも多くやる企業なので総還元性向は100%を超えることもしばしば。キャッシュのやりくりをしながらなるべく投資家に還元しようという姿勢が見える企業です。
連続増配としては12年ですが、上場以来100年以上配当を切らせたことはなく、減配もしたことがありません。安定的な高配当は期待して良いと思います。

直近配当利回り:3.00%
ゼネラル・ミルズ(GIS)の株価、チャート分析
とりあえずリアルタイムチャートのリンク置いておきます。
過去の最高値、最安値

17年に入ってちょっと落ちてきている、米国株の中では出遅れ感のある銘柄になっています。
リーマンショックの影響も全体から見れば微々たるもので、特に補助線など引かずとも分かるくらい、長らく安定した右肩上がりのチャートを描き続けてきました。
- 最高値:72.75ドル(16年7月)
- リーマンショック後最安値:23.18ドル(09年1月)
リーマンショック前の格安水準には戻りそうもないので、上限下限設定はこれでいいと思います。単純に2で割ると48ドルなので、50ドル前後だとリスクリワード的にちょうどいい水準になります。
もちろん、長期で配当が続くことにかけて、(ちょうど今落ちてきていることもあり)早めのタイミングで継続購入もありかもです。
今後の値動き予測
5年チャート

中央に引いた47ドル~59ドルの狭いレンジが結構意識されていそうで、ちょうど今そのレンジの中に入ってきました。ここに捕まっているうちに買いタイミングは何度かやって来そうな感じがします。
1年チャート

7期連続の減収でしたが、16年後半から特に不調が顕著です。下げ止めるネタを待っている状態で、しばらくズルズルと下がって行くのではと思います。
ゼネラル・ミルズ(GIS)の投資戦略
まとめ。
- ハーゲンダッツやとんがりコーンといった市場シェア1位or2位の有名ブランドを複数保有する企業だが、ここ2年くらい減収が続いている。
- 今後の事業ポートフォリオとしては、健康志向に合わせたオーガニック、グルテンフリー、アレルゲンフリーの製品を軸にしようとしている。
- 100年以上減配なしという株主還元意欲の強い企業で、今後もよっぽどのことがない限り続くと思われる。
- チャートは長期で見れば非常に安定している一方、16年後半からは右肩下がり。
回答
直近で売上が落ちている状況で株価も売り込まれていますが、老舗のブランド力+市場自体の拡大と、それにニーズにマッチした製品への原材料変更で、待っていればそのうち反転しそうに見えました。
反転しないでもしばらく配当や自社株買いによる還元は続くと予想されるので、そうして損益分岐点を下げてくれます。長期チャートもほとんど波のない値動きで安心感は強いです。
落ちてきているのでリスクリワードも悪くなく、どこかで仕込みたい銘柄です。安く買ったディフェンシブ銘柄なんてそれこそ一生のお宝銘柄になりますからね。
個々のM&Aにはほとんど触れていませんが(例えばヨープレイトも11年に買収したもの)、高シェアのブランド数が安定した事業基盤を生むという構造さえ押さえられれば問題ないと思っています。
ヨープレイト関連について、購入記事にもう少し詳しい情報を取り上げています。合わせてご確認ください。

これまで調査してきた米国株の個別銘柄記事リストをまとめました! 企業名クリックで各詳細記事に飛ぶことが出来ます。
| 企業名 (リンク先は分析記事) | ティッカー | 業種区分 | 主力事業、ブランド |
|---|---|---|---|
| アマゾン | AMZN | IT | ネット小売、クラウド |
| アルファベット/グーグル | GOOGL | IT | 広告(検索)、AI |
| アップル | AAPL | IT | iphone |
| マイクロソフト | MSFT | IT | OS、Office365 |
| フェイスブック | FB | IT | 広告(SNS) |
| IBM | IBM | IT | クラウド、AI |
| インテル | INTC | IT | 半導体(PC、サーバ) |
| クアルコム | QCOM | IT | 半導体(モバイル) |
| エヌビディア | NVDA | IT | 半導体(GPU) |
| オラクル | ORCL | IT | ソフトウェア(DB) |
| オクタ | OKTA | IT | オクタ |
| シスコ | CSCO | IT | ネットワーク機器 |
| アリババ・グループ | BABA | IT | タオバオ、Tmall、アリペイ |
| テンセント | HKG00700 | IT | テンセント |
| バイドゥ | BIDU | IT | 百度 |
| ビザ | V | 金融 | 決済インフラ |
| マスターカード | MA | 金融 | 決済インフラ |
| アメリカン・エキスプレス | AXP | 金融 | 決済インフラ |
| スタンダード&プアーズ | SPGI | 金融 | 格付け機関 |
| ムーディーズ | MCO | 金融 | 格付け機関 |
| ブラックロック | BLK | 金融 | 運用会社 |
| ウェルズ・ファーゴ | WFC | 金融 | 商業銀行 |
| JPモルガン・チェース | JPM | 金融 | 商業銀行、投資銀行 |
| シティグループ | C | 金融 | 商業銀行、投資銀行 |
| ウエストパック銀行 | WBK | 金融 | オーストラリア銀行 |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 金融 | バークシャー |
| AT&T | T | 通信 | モバイル通信 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信 | モバイル通信 |
| ネットフリックス | NFLX | 通信 | 動画配信サービス |
| ウォルト・ディズニー | DIS | 通信 | ディズニー、ESPN |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | 医薬品(ステラーラ)、バンドエイド他 |
| メドトロニック | MDT | ヘルスケア | 医療機器(ペースメーカー他) |
| アボット・ラボラトリーズ | ABT/ABBV | ヘルスケア | 栄養補助食品、医薬品(ヒュミラ他) |
| ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | BMY | ヘルスケア | 医薬品(オプジーボ他) |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | 医薬品(プレブナー、リリカ他) |
| メルク | MRK | ヘルスケア | 医薬品(キイトルーダ他) |
| ギリアド・サイエンシズ | GILD | ヘルスケア | 医薬品(ハーボニー他) |
| CVS ヘルス | CVS | ヘルスケア | 薬局、PBM |
| ユナイテッド・ヘルス | UNH | ヘルスケア | 医療保険、PBM |
| P&G | PG | 生活必需品 | ビューティー(パンテーン、SK-II)他 |
| ユニリーバ | UL | 生活必需品 | パーソナルケア(Dove、LUX) |
| コルゲート・パーモリーブ | CL | 生活必需品 | オーラルケア(歯磨き) |
| コカ・コーラ | KO | 生活必需品 | コカ・コーラ |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | ペプシ・コーラ |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 生活必需品 | ハーゲンダッツ |
| クラフト・ハインツ | KHC | 生活必需品 | チーズ、ケチャップ |
| マコーミック | MKC | 生活必需品 | スパイス |
| ホーメルフーズ | HRL | 生活必需品 | SPAM |
| マクドナルド | MCD | 生活必需品 | マクドナルド |
| スターバックス | SBUX | 生活必需品 | スターバックス(スタバ) |
| ウォルマート・ストアーズ | WMT | 生活必需品 | 大型店舗小売 |
| コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | 会員制小売 |
| ホーム・デポ | HD | 生活必需品 | DIY小売 |
| フィリップ・モリス | PM | 生活必需品 | たばこ(マルボロ) |
| アルトリア・グループ | MO | 生活必需品 | たばこ(マルボロ) |
| レイノルズ・アメリカン | RAI/BTI | 生活必需品 | たばこ |
| アンハイザー・ブッシュ・インベブ | BUD | 生活必需品 | バドワイザー |
| ナイキ | NKE | 生活必需品 | スニーカー(ナイキ・エア) |
| ギャップ | GPS | 生活必需品 | GAP、オールドネイビー |
| エクソン・モービル | XOM | エネルギー | 石油メジャー |
| シェブロン | CVX | エネルギー | 石油メジャー |
| ロイヤル・ダッチ・シェル | RDS.B | エネルギー | 石油メジャー |
| ボーイング | BA | 資本財 | B787ドリームライナー |
| ロッキード・マーティン | LMT | 資本財 | ステルス戦闘機F-35 |
| ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 資本財 | 航空機エンジン、エレベーター |
| キャタピラー | CAT | 資本財 | 建設機械(油圧ショベル他) |
| ゼネラル・エレクトリック | GE | 資本財 | 照明、航空機エンジン |
| テスラ | TSLA | 自動車 | 電気自動車(EV) |
| スリーエム | MMM | 素材 | ポストイット |
| デューク・エナジー | DUK | 公共 | 電力、ガス |