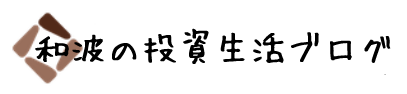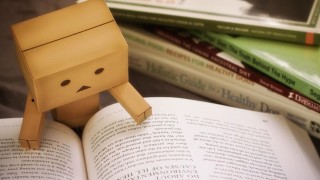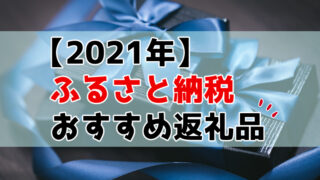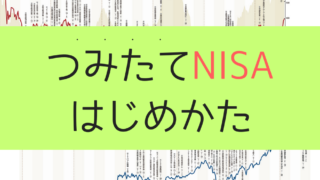今回はロッキード・マーティン(LMT)のファンダメンタル、チャート分析をやっていきたいと思います。
軍事産業世界一、二位を争う巨大企業で、売上のほとんどが軍事関係、特に米国政府向けのビジネスになります。
ロッキード・マーティン(LMT)の事業内容
ビジネスを3Cで分解してみましょう。
事業内訳
民間事業からは撤退しているため、ほとんど完全な軍事企業になります。戦闘機、ミサイル、衛星など、幅広く製品を有しています。
事業としては以下の4セグメントに分かれます。

(出典:ロッキード・マーティン IR)
- Aeronautics(軍用航空機):全体の37.6%を占めるロッキード・マーティンの主力事業です。ステルス戦闘機F-35が好調で増収増益(F-35が全体の23%を占めます)、その他にもF-22のような世界的な軍用機が主力製品です。また、航空機事業の中の米国政府割合は66%となっているようです。
- Missiles and Fire Control(ミサイルと射撃統制):全体の14%弱を占める略称MFCは、ミサイルやロケット、有人・無人システムの開発を行います。HPには50の製品一つ一つについて詳細な説明があります。同部門のうち61%は米国政府が顧客になります。あとは利益率が15%と他と比べて高いですね。
- Rotary and Mission Systems(軍事システム):28.4%を占めます。16年に1.5倍近く急増していますが、これはシコルスキーの買収効果みたいですね。シコルスキーのヘリコプターの他、ミサイル防衛システム、レーダー、サイバーソリューション等多くの事業を含みます。利益率は10%を切っており、あまり良い数字ではありません。ここの米国政府割合は68%。
- Space Systems(宇宙システム):20%弱を占めています。通信衛星システム、気象衛星など。米国政府への売上が91%とほとんどを占めます。
宇宙システムも防衛・軍事産業の分類ではありますが、それらを除いて約80%が純粋な軍事部門というところがロッキード・マーティンの特徴です。
あとはボーイングで見たものと同じ切り口でそれぞれ見ておきましょう。
- 海外売上比率:四季報によると米国73.1%、海外26.9%です。米国内比重が高いと言えます。
- 官需と民需:民間航空機事業からは完全に撤退していますので、ほとんどが官需になります。ここがボーイングとは大きく異なる点で、あちらは官需で採算取れなければ民需に傾くことが出来ますが、ロッキード・マーティンは小さな軍需の中で稼ぐしかありません。
- 米国政府比率:レポートには16年度で71%にあたる472億ドルが米国政府からとあります。
米国政府動向の影響大
元々資本財株は景気循環株と言われており、景気変動の影響を受けやすい銘柄です。加えて、ロッキード・マーティンのお得意様は米国政府になりますので、将来の見通しは国策が絡んで度々変化していきます。
つまり、米国政府の動向に注視しなければなりません。
ロッキード・マーティンとは長期契約を結んでいますし、国策的にも潰せない企業です。短期で受注の増減はあれど、企業存続という観点で言えばリスクはないでしょう。
競合
米防衛大手5社はボーイング、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、レイセオン、ゼネラル・ダイナミックスです。
ボーイングは記事を書きました。

売上高全体ではボーイングのほうが大きいですが、ボーイングの軍事事業比率は3割以下なので、8割が軍事関係のロッキード・マーティンのほうが規模は大きいです。
ユナイテッド・テクノロジーズは軍事産業を含めたコングロマリットで、ここも別途記事を書くつもりです。
レイセオンはトマホークで有名で、ミサイル売上高世界一の企業です。ここもロッキード・マーティン同様に、ほぼ軍事部門のみになります。

(出典:東洋経済オンライン)
市場
米国政府の軍事予算は世界一ですし、米国政府の後ろ盾で(特に日本とか)海外への武器輸出も優位に進みます。16年には中東(カタールやバーレーン)への戦闘機輸出が承認されたため、中等も大きな顧客になり得ます。
ボーイングの記事にも載せましたが、米国の軍事費推移を再掲します。出来れば通貨をドル表記で統一してほしかった(笑)

(出典:防衛白書)
オバマ政権化で緩やかに減少気味だったこともあり、ここ数年の5大防衛大手の売上高は米国で横ばい、米国外では10%増加と、米国外市場が牽引してきました。ロッキード・マーティンも、国外割合が低いからと無視してはいけないということですね(日本のGDPで輸出割合が低くとも成長寄与度が高いという理屈と同じです)。
まあでも世界全体で米国軍事費が占める割合は36.3%と圧倒的です。ここがじゃぶじゃぶお金を使いますので、安定した業績は維持し続けると予想できます。

(出典:ガベージニュース)
あと、色々心配されていたトランプですが、軍事費を6兆円増やすことを表明しました。テロとの戦い等で怪しい政治状況になっており、私達にとっては嫌な話ですが防衛大手にとっては追い風が続きます。
参考トランプ大統領、軍事費6兆円規模増額の方針 「歴史的拡大だ」
リスク要素
ボーイングの軍事関連のリスクとほとんど同じです。
資本財の投資収益率はそれほど高くない
伝統的に、航空業界は景気循環するものとされています。つまり、好景気で良く見える株ということです。
ところが、シーゲル先生の赤本では、資本財の収益率は10.22%と市場平均を下回っているとの調査結果が書かれています。

ということで、一般論ですが長期投資にはやや不向き、不景気に仕込んで好景気に売ったほうが良い銘柄ということになります。
トランプ政権
一般的に対外強硬姿勢の強い共和党政権で、軍事部門は業績が良くなると言われています。トランプは共和党らしからぬ外国軍事を無視するタイプと見ていたのですが、どうにもそうではなかったようで、失礼しました。
オバマ政権下では特に前半期に低迷していましたが、そもそもの成り立ちで、民主党は自国の福祉政策を優先するものだから仕方ないですね。
一年前くらいの記事で更新もしていないのですが、ヒラリーとトランプ、それぞれ大統領になったら上がりそうな株を調査しています。ヒラリーの記事は当ブログの閲覧数で累計2位となっています。


米国外の成長余地
上でも書いたように、ここ最近の成長を担ってきたのは米国外への輸出ですが、今度どうなるか不透明です。
アジア圏においても、中国ロシアが米国対抗で自国の航空機メーカーを育てようという機運があります。中東進出の話も、中国がサウジアラビアへ無人機を輸出したりと地盤を脅かす動きをしています。
シコルスキー買収とリスク
15年にユナイテッド・テクノロジーズからシコルスキーを買収しています。シコルスキーはヘリコプターの製造をやっていた企業ですが、財務について内部統制監査がついています。
ロッキード・マーティン(LMT)の財務分析
PL
売上は若干の変動がありますが、利益はほとんど横ばいです。利益率も10%を下回っていて、このセクターってあまり儲からないのかなと思ってしまいます。

ROEが異常だったり、EPSがずっと右肩上がりに成長しているのは自社株買い効果ですね。

BS
自己資本はほとんどありません。トップシェアかつ政治的に潰せない軍事産業とはいえ、ずいぶんなバランスシートですよね……。固定負債も多くなっています。


CF
キャッシュフロー上ではかなり余裕があります。思ったほど投資は大きくなく、常に一定率のFCFを確保しているようです。

株主還元指標
自社株買いと配当を1:1くらいでやっている企業で、DPSの右肩上がりは良い傾向だと思います。というかDPS自体が非常に高いですね。配当性向50%なので増配余地も十分です。

直近配当利回り:2.48%
株価も高騰していることもあり、利回りはそれなりの水準に落ち着いています。
ロッキード・マーティン(LMT)の株価、チャート分析
とりあえずリアルタイムチャートのリンク置いておきます。
過去の最高値、最安値

上がりすぎーなチャートですね。13年なんか1年間陽線しか出てないんじゃないだろうか。
- 最高値:273.11ドル(現在)
- 最安値(リーマンショック後):57.41ドル(2009年)
こんな突き抜け方をされるともうポイントが見えないです。
今後の値動き予測
5年チャート

きれいな平行線が引けました。長い上昇トレンドの中にあります。
1年チャート

直近だけ見るなら275ドルに3回当てていますが、これだけ勢いあったらここでは止まらないでしょうね。300ドルの目安か、あるいはバッドニュースが来てどう動くかだと思います。
ロッキード・マーティン(LMT)の投資戦略
まとめ。
- 売上の80%が純粋な軍事部門、売上の71%が米国政府という偏った事業区分を有している、世界一の軍事企業。
- 米国政治の影響が大きく、トランプ政権で軍事予算の扱いには要注目。
- 最大手のわりに利益率は高くなく、バランスシートもあまり美しくない。
- チャートとしては高騰中で、5年間きれいな上昇トレンドが続いている。
段々まとめが雑になっているような……。
回答
特殊な産業というイメージがやはり強いですね。結局は米国政府次第というロッキード・マーティン。国の防衛に関わるところに他国の企業が入り込む余地はなく、そもそもの技術力で圧倒していますので、立場は安泰だと思いました。
とはいえ、いかに米国政府の軍事予算が莫大だと言っても、やはり民需に比べて極端に狭い市場であることは間違いないです。同盟国に対して武器を輸出することで成長余地も残っていますが、米国政府に比べればそこまで大きな規模ではありません。
予算は限られていて政府からの値下げ圧力もあり、利益率が大幅に改善されるのは期待しにくいと思っています。何気にこれだけ株価が上がっていて利回り2.5%近くあるのは驚きなのですが、どちらにしても、上昇トレンドが終わってから検討としたいです(いつになるやら)。
これまで調査してきた米国株の個別銘柄記事リストをまとめました! 企業名クリックで各詳細記事に飛ぶことが出来ます。
| 企業名 (リンク先は分析記事) | ティッカー | 業種区分 | 主力事業、ブランド |
|---|---|---|---|
| アマゾン | AMZN | IT | ネット小売、クラウド |
| アルファベット/グーグル | GOOGL | IT | 広告(検索)、AI |
| アップル | AAPL | IT | iphone |
| マイクロソフト | MSFT | IT | OS、Office365 |
| フェイスブック | FB | IT | 広告(SNS) |
| IBM | IBM | IT | クラウド、AI |
| インテル | INTC | IT | 半導体(PC、サーバ) |
| クアルコム | QCOM | IT | 半導体(モバイル) |
| エヌビディア | NVDA | IT | 半導体(GPU) |
| オラクル | ORCL | IT | ソフトウェア(DB) |
| オクタ | OKTA | IT | オクタ |
| シスコ | CSCO | IT | ネットワーク機器 |
| アリババ・グループ | BABA | IT | タオバオ、Tmall、アリペイ |
| テンセント | HKG00700 | IT | テンセント |
| バイドゥ | BIDU | IT | 百度 |
| ビザ | V | 金融 | 決済インフラ |
| マスターカード | MA | 金融 | 決済インフラ |
| アメリカン・エキスプレス | AXP | 金融 | 決済インフラ |
| スタンダード&プアーズ | SPGI | 金融 | 格付け機関 |
| ムーディーズ | MCO | 金融 | 格付け機関 |
| ブラックロック | BLK | 金融 | 運用会社 |
| ウェルズ・ファーゴ | WFC | 金融 | 商業銀行 |
| JPモルガン・チェース | JPM | 金融 | 商業銀行、投資銀行 |
| シティグループ | C | 金融 | 商業銀行、投資銀行 |
| ウエストパック銀行 | WBK | 金融 | オーストラリア銀行 |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 金融 | バークシャー |
| AT&T | T | 通信 | モバイル通信 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信 | モバイル通信 |
| ネットフリックス | NFLX | 通信 | 動画配信サービス |
| ウォルト・ディズニー | DIS | 通信 | ディズニー、ESPN |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | 医薬品(ステラーラ)、バンドエイド他 |
| メドトロニック | MDT | ヘルスケア | 医療機器(ペースメーカー他) |
| アボット・ラボラトリーズ | ABT/ABBV | ヘルスケア | 栄養補助食品、医薬品(ヒュミラ他) |
| ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | BMY | ヘルスケア | 医薬品(オプジーボ他) |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | 医薬品(プレブナー、リリカ他) |
| メルク | MRK | ヘルスケア | 医薬品(キイトルーダ他) |
| ギリアド・サイエンシズ | GILD | ヘルスケア | 医薬品(ハーボニー他) |
| CVS ヘルス | CVS | ヘルスケア | 薬局、PBM |
| ユナイテッド・ヘルス | UNH | ヘルスケア | 医療保険、PBM |
| P&G | PG | 生活必需品 | ビューティー(パンテーン、SK-II)他 |
| ユニリーバ | UL | 生活必需品 | パーソナルケア(Dove、LUX) |
| コルゲート・パーモリーブ | CL | 生活必需品 | オーラルケア(歯磨き) |
| コカ・コーラ | KO | 生活必需品 | コカ・コーラ |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | ペプシ・コーラ |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 生活必需品 | ハーゲンダッツ |
| クラフト・ハインツ | KHC | 生活必需品 | チーズ、ケチャップ |
| マコーミック | MKC | 生活必需品 | スパイス |
| ホーメルフーズ | HRL | 生活必需品 | SPAM |
| マクドナルド | MCD | 生活必需品 | マクドナルド |
| スターバックス | SBUX | 生活必需品 | スターバックス(スタバ) |
| ウォルマート・ストアーズ | WMT | 生活必需品 | 大型店舗小売 |
| コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | 会員制小売 |
| ホーム・デポ | HD | 生活必需品 | DIY小売 |
| フィリップ・モリス | PM | 生活必需品 | たばこ(マルボロ) |
| アルトリア・グループ | MO | 生活必需品 | たばこ(マルボロ) |
| レイノルズ・アメリカン | RAI/BTI | 生活必需品 | たばこ |
| アンハイザー・ブッシュ・インベブ | BUD | 生活必需品 | バドワイザー |
| ナイキ | NKE | 生活必需品 | スニーカー(ナイキ・エア) |
| ギャップ | GPS | 生活必需品 | GAP、オールドネイビー |
| エクソン・モービル | XOM | エネルギー | 石油メジャー |
| シェブロン | CVX | エネルギー | 石油メジャー |
| ロイヤル・ダッチ・シェル | RDS.B | エネルギー | 石油メジャー |
| ボーイング | BA | 資本財 | B787ドリームライナー |
| ロッキード・マーティン | LMT | 資本財 | ステルス戦闘機F-35 |
| ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 資本財 | 航空機エンジン、エレベーター |
| キャタピラー | CAT | 資本財 | 建設機械(油圧ショベル他) |
| ゼネラル・エレクトリック | GE | 資本財 | 照明、航空機エンジン |
| テスラ | TSLA | 自動車 | 電気自動車(EV) |
| スリーエム | MMM | 素材 | ポストイット |
| デューク・エナジー | DUK | 公共 | 電力、ガス |