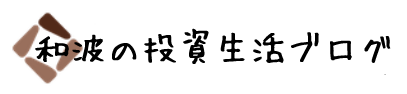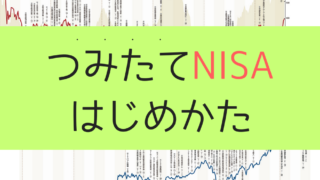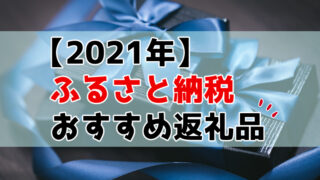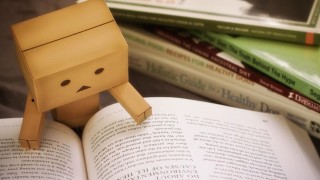バークシャー・ハサウェイの会長、ウォーレン・バフェットの投資論や思考法は既に広く知れ渡っています。一方で、バークシャーの副会長であるチャーリー・マンガーの投資論についてはそこまで知られていないと思います。
チャーリー・マンガーはバフェットの7歳上で、バフェットの投資論に大きな影響を与えてきました。
グレアムの考え方の限界を超えるためには、チャーリー・マンガーの思考の力が必要だった。
出典:ウォーレン・バフェット
今回、日経BP様より「マンガーの投資術」の見本をいただきました。本当にありがとうございます。
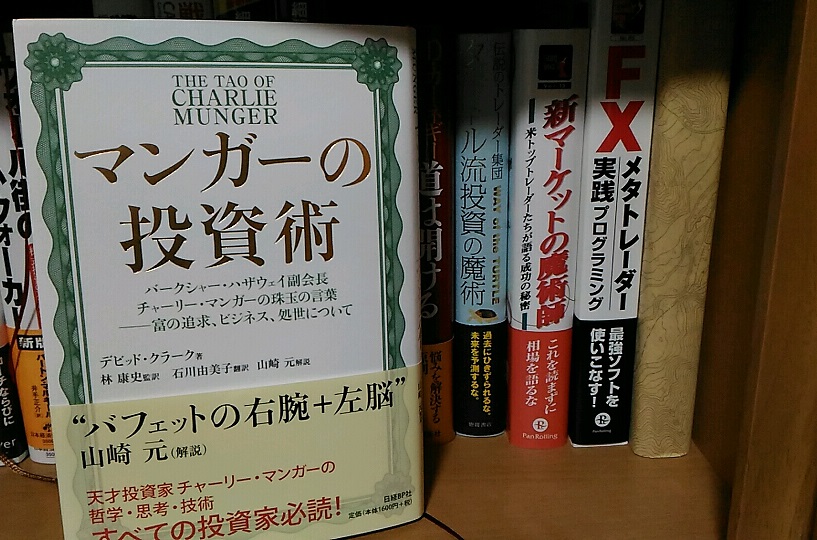
発売は9/11だそうです。アマゾンで予約受付中。
連絡をいただいたとき、正直巷に溢れてるハウツー本とかだったら要らないなと思ったんですが……調べてみたら著者デビッド・クラークって「億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術」と同じ人じゃん! と分かってソッコー返信しました(笑)
書評書いてるといいことがあるものですね。
バフェットとマンガ―
本書の構成はマンガ―の発言に対して実際に過去とった行動や意図を解説という形で挟んでいくものです。
以下読んで色々考えたこととか。本書と関係ない内容を多分に含みます。
バフェットと同じ哲学
長年パートナーやってるだけあって、二人の考え方は似ていますね。面白いのはやっぱりベンジャミン・グレアムとの相違です。
グレアムの割安株投資は「本源的価値よりも安く買うこと」であり、出口戦略は本源的価値を株価が超えた時点としています。
いつか相場が企業の本源的価値に修正することに賭けるやり方で、安く買う=安全マージンを用意するというところにはグレアムの大恐慌の経験が活かされています。
ところがこれは、長期で企業価値を拡大し続ける永久保有銘柄も平均値で売却してしまうということです。せっかくいいところで買ったのに、大きく利益を取れないのです。
将来も利回りが拡大する前提であれば、現在の株価だけを割高割安の判断材料にして売買するのはもったいない。ここの問題は前にPERについて書いた通りですね。

マンガ―とバフェットはそのような優良株を「株式債券」と呼び、安全性と利回り成長を料率させた擬似的な債券と捉えています。
彼らが一生売るつもりはないと謳うコカ・コーラ(KO)は2015年に5億ドル以上もの配当をバークシャーに支払い、投資額に対する現在の配当利回りは年間40%以上という計算になります。凄いですね……^^;
適正な価格で売られている偉大な会社は、割安な価格で売られているそこそこの会社よりも優れている。
出典:チャーリー・マンガー
かつても金融やITという新市場が次々開拓されていく中、結局最後に笑ったのは誰もが知っている「退屈な」会社に投資してきたバフェットとマンガ―でした。
歴史は繰り返すのか、はたまた今度は利益もついてきているから様相が変わっているのか。アップルに投資したバークシャーはそろそろ後者と考えているかもしれません。
優れた経営者=優れた投資家
投資というのは最適なリソースの振り分けを考えるものであって、優れた経営者というのは優れた投資家にもなるんでしょうね。
- 分散投資? 寝言は寝てから言え集中投資だ:本当にいい株はそんなにたくさんない
- 行けそうだったら全力で行け、それまで必死に耐えて待て:本当にいいタイミングはそんなにたくさんない
- ビビるな:儲けられる人はそんなにたくさんいない
書き方は全然違いますが(笑)、まあ言いたいことは同じはずです。勝負どころでちゃんと勝負することが大切ですね。
キャッシュポジション
マンガーはいつ金融危機が発生してもいいようにキャッシュポジションを持っています。リターンが低くなることは承知の上で。
バフェットとマンガーは、暴落の度に後の主力となる株を買っています。知ってましたけど、改めて結果を振り返ると本当に上手いですよね。個別に分析した銘柄はリンクを貼っています。
- 1962年のケネディ暗殺時のショックでバークシャーを購入
- 1973年のオイルショックでワシントン・ポストを購入
- 80年前後の政策金利変動の時代にはゼネラルフーズ(クラフトハインツ:KHC)、RJレイノルズ(レイノルズアメリカン:RAI)を購入
- 87年のブラックマンデーにコカ・コーラ(KO)を購入
- 90年代前半に業績の悪化していた銀行株の中でウェルス・ファーゴ(WFC)を購入
- 90年代後半にITバブルで見向きもされなくなったデイリークイーン、ネットジェッツ、ジェネラル再保険を購入
- 2001年のITバブル崩壊&同時多発テロでムーディーズ(MCO)、HRブロック購入
- 2007年のサブプライムショック以降、ゼネラル・エレクトリック(GE)、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカを購入
今のバフェット銘柄はこんな感じです↓
| 企業名 | ティッカー |
|---|---|
| Apple Inc. | AAPL |
| Bank of America | BAC |
| Coca-Cola Co. | KO |
| American Express Company | AXP |
| Kraft Heinz Company | KHC |
| Moody’s | MCO |
| Wells Fargo & Co. | WFC |
| U.S. Bancorp. | USB |
| Davita | DVA |
| Charter Communications | CHTR |
| おまけ:バークシャー・ハサウェイ | BRK.B |
さて、このキャッシュを常に持って待っているというやり方、インデックス投資家としてはどうなんでしょうね。
キャッシュポジションを持つということは、私としてはこうした暴落時に買い向かうことで結果的にリターンを大きくしたいという意識があると思っています。
私はインデックス投資家ではありませんので、キャッシュを一定割合持っているのは、債券代わりの安全資産という意味と、暴落時に拾い物をしたいという意味があります。こうしたことを考えないのであれば、ほぼフルインベストメントが最適解なのかなと思いますね。
バフェットは自身の遺産を妻に相続する場合、資産の9割をS&P500連動ETFに、残りを短期債券に回すという方針を指示したそうです(前記事にしたものです)。
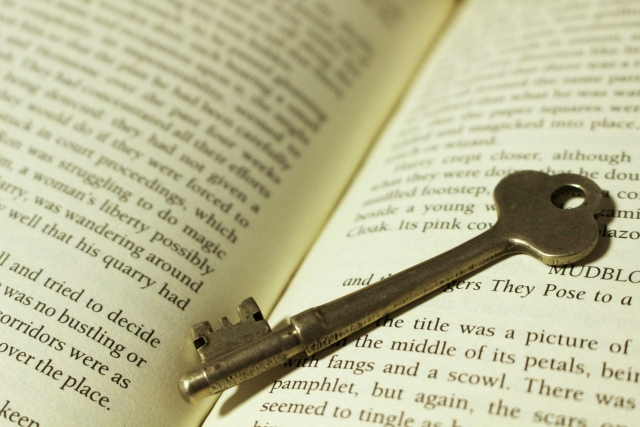
この辺色々見ながら最適な資産配分を考えたいものです。
金融危機とその後の回復
景気はサイクルするもので、米国市場というのは10年で1サイクル回しているというデータがあります。以前見た通りです。

リーマンショックは世界のGDPが約1%減少するという恐ろしい危機でしたが、1929年の大恐慌はその比ではなく、なんと世界GDPの15%が消し飛びました。米国だけでも貿易は50%減、失業率25%という壊滅的な状況でした。
危機というのは私達が想定しているより遥かに恐ろしいもので、しかしながらそれでも立ち直る仕組みも資本主義経済は内包しているとも言えます。
バークシャー・ハサウェイもこの50年の間に株価半減が3回あったそうです。しかしいずれも元に戻り、それ以上に増えていきました。引用させていただきますが、下の部分が特に重要だと思います。
一九ニ九年と三二年の大暴落の後、ダウ工業株平均が完全に回復したのは一九五四年のことだったが、コカ・コーラやフィリップ・モリスのような優良銘柄は一九三六年には暴落前の水準を取り戻していた。
出典:マンガ―の投資術
本源的価値に基づいて株価が決まるということは、危機で一度売られても、やがて戻るということです。慌てずに暴落に対処しようということですね。
「消費者独占力が強い会社が良い」、「設備投資は少ないほど良い」、「どんな経営者でも悪い事業を上手くやるのは難しい」……etc、バフェットと似た投資理論を持っているので、正直本の内容自体はバフェットファンにはお馴染みの点も多いと思います。
ただ、80年代90年代の昔の話、バフェットやマンガーの投資理論が組み上がった背景や実例があちこちに出てくるので、読み物として面白かったですね。
色々なヒントが詰まっている良い本だと思います。最後の山崎氏の解説も見事。
興味のある方は是非。