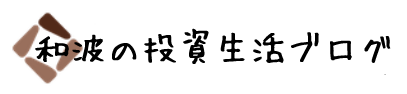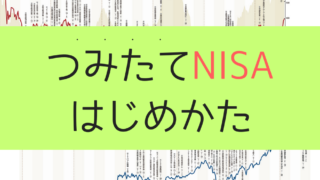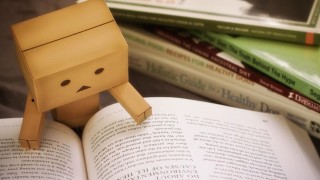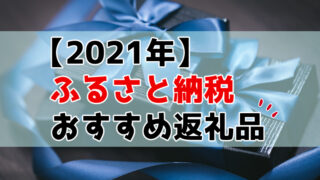最近でもない話ですが、静かな退職(Quiet Quitting)というのが若い人の間で流行りというか、多いらしいですね。
2022年にアメリカのキャリアコーチが発信し始めた「Quiet Quitting」の和訳で、会社を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態、とされています。
静かな退職という働き方#1
私がやっていることもそれに該当するんだろうなと思います。たぶん。きっとそう。
私が入社して間もない頃は、有給全消化したのが部で私一人だったという話が管理職の会議で出ていたとか聞きましたが、それと比べれば随分と働きやすい世の中になってきたもんだなと思います。
まあパレートの法則よろしく、どこの組織でも全体の2割が残り8割を支える構図が出来上がるものなので、自分が8割に属していることを自覚してしっかり寄りかかっていくのも賢い一つの生き方でしょう。
昔の記事で「出来る人に見られたい」というしょうもないプライドを捨てようみたいなこと書いてたんですが、静かな退職には間違いなく求められる資質ですね。

目次(クリックで飛びます)
本業+副業は強い
とはいえ、周りに不和をばらまきながら職場に居座り続けるのも精神的にはあまりよくないですよね。
理想は最低限の仕事をこなしつつも感謝されること。
なので、この最低限度の仕事量というものをどれだけコントロールできるかが重要なんじゃないかと思っています。
専門的なスキルを持っていると強い
会社は目標が決まっていてそこに準じて仕事は降ってくるわけで、自分で自分の仕事量をコントロールするのは簡単じゃないですよね。
そこで重要なのが専門的なスキルで、あまり他の人が出来ない仕事をしていると、自分の仕事量がどのくらい大きいのか他の人が測りにくくなります笑
つまり「自分的にはそんな大変じゃないけど他の人から見たら大変そう」というギャップを作る感じですね。
副業で身につけたスキルを活かす
で、そういう専門的なスキルを身に着けるのにも副業はおすすめです。
まあ本来は本業で得たスキルを活かして副業や独立という流れのほうがスムーズなのかもしれませんが、私の場合は逆でした。
仕事のために仕方なく勉強した人と、好きで金にもなるから平日夜や休日にひたすら研鑽してきた人では、同じ1年を過ごしても身につくものに雲泥の差が出るでしょう。
万が一のときのリスクヘッジもかねて、副業でお金を稼ぎつつ、スキルアップもして相乗効果が生まれたら言うことなしですね。
AIやらなんやらで仕事は年々効率化されているのにいつまでも勤務時間が同じだったら、そのほうがおかしいのです(クリエイティブすらもAIの強みになりつつありますね)
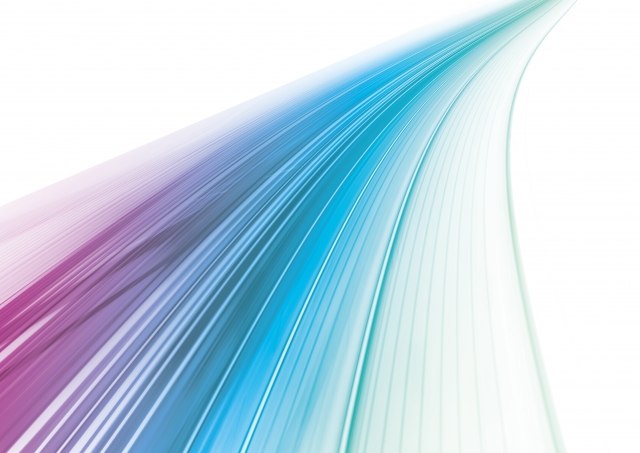
下の記事は新卒時代の私の飲み会経験ですが、この時期はまだ飲み会とか残業とか古い習慣が当たり前でした。この説教していた人は数年後に辞めてどこかへ転職しました。
社会人に必要なのは付き合う根気じゃなくて断る勇気じゃないかと思っていたことがあります。最近はご時世的にもコンプラ的にもそういう機会自体が減りましたかね。

好きを仕事に出来るほど稼げなくても、続けられるくらい稼げるといろいろラクになります。収入が増えてきたら運用に回せるとなお良し。

ではでは。